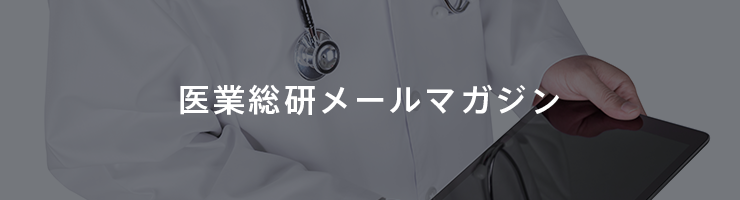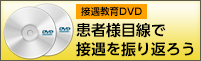本誌5号で紹介した豊島区要町に開業した岡本整形外科(岡本重雄院長)に隣接する区画で、平成22年11月にオープンした『要町やまもと眼科』。院長の山本禎子先生は、基幹病院や大学で特に網膜硝子体疾患の工キスパートとして活躍された後に、山形大学医学部眼科学講座教授に就任。臨床・研究双方に数多くの業績を残され、今回地元での開業を迎えた。
■まず、先生が医師を目指された動機をお聞かせください。
父が産婦人科の勤務医、母が眼科の開業医の家庭でしたから、両親を見てやりがいのある仕事だな、と子どもの頃から思っていました。
■実際に医師になられて、この職業をどう思われましたか。
女性が責任のある仕事を持ち、男性と同等に正当な評価を受ける、という意味で医師は素晴らしい職業です。目的は患者さんの疾患を治すと先生いう一点にあるわけで、結果が全ての仕事です。経歴も何も関係なく、治した者が勝者です。評価するのは患者さんですから非常にフェアな職業ですね。
■眼科を志望されたのは、お母様の影響でしょうか。
将来、実家をサポートしたい、という気持ちは当然ありましたが、それよりも、学生時代に見た眼のきれいなことに感激したことです。
■キレイ、というと!?
眼底の美しさです。これは人の臓器で最も美しいのではないかと感じました。それで眼科を究めようと決心しました。大学勤務の頃、ポリクリで来る学生たちに硝子体手術を見せる機会があると、手術顕微鏡で眼底を見せます。皆本当に感激してますね。
患者さんの「ありがとう」が開業医の喜び
■大学では教授のポストにおられたのですが、あえて開業を決意されたきっかけは。
両親も高齢化し現役を離れ、いつかは実家に帰らなければ、とは思っていました。
正直なことを言えば、大学でやり残したことは山ほどありましたし、辞めるのは同僚にも迷惑がかかるのでためらいました。大学の医療は臨床と同時に、研究機関としての機能が重視される。これは、やりがいでもあるのですが、患者さんの病気を治す以外に、データを解析するという作業が加わってきます。さらに、指導職になると、若手の担当医が連れてくる患者さんを次々に診断して治療方針を指示し、それで手が離れてしまう。例えば手術をしても、終わったとたんに主治医に引継ぎ、すぐに次の患者さんへ。これが日常なわけです。これでは患者さんの生の声が伝わってきません。そういうことに、ふと、寂しさを感ました。医師として、患者さんの話をゆっくりと聞いてあげたい。もっと日常に関わる相談にも耳を傾け、最初から最後まで患者さんに密接した医療を提供したい、そんな気持ちを常に持っていました。
■開業によってそれが実現できましたか。
患者さんには待ち時間も心地よく過ごしていただけるように、待合室のデザインやスタッフの細かな対応にも気を配りました。一人ひとりの患者さんとじっくり向かい合って治療し、患者さんやご家族から直接「ありがとう」と言われることに、毎日喜びを感じています。
医業総研との出会いが、開業の出発点
■ご実家の眼科クリニックを承継される選択もあったのでは。
いつまで経っても帰ってくる気配のない娘に呆れて、5年前に閉院しました(笑)。母は高齢でしたし、クリニックは住宅地のなかにありましたから、立地的にも決して良いとはいえなかったこともあります。
■医業総研のコンサルは納得いくものでしたか。
実家から徒歩圏内のこの物件に目を付け、仲介する不動産会社の紹介で医業総研を知りました。それまでは、コンサルタントに依頼するなど考えてもいなかったのですが、結果、本当に頼りになりました!開業に際して何をどう進めたら良いものか、まるで手探りでしたし、何とかなるだろうと甘く考えていた部分もあります。その甘さを担当の小畑さんに鋭く指摘されたことで、開業の意識がリアルになりました。そういう意味では、医業総研との出会いが、開業の出発点だったといえます。
■これからの地域医療とクリニックのありかたについて、どうお考えですか。
開業医はより専門性を打ち出して、大学病院に劣らない、医療水準を持つべきです。勤務医は、毎日膨大な数の外来診療と入院患者のケアに追われて疲弊しているのが現実です。通院治療で治せる患者さんを、高度なレベルを持ったクリニックが担うことができれば病院の負担が軽減されるし、それが病診双方の信頼関係を高める理想的な機能分化ではないでしょうか。そういうスキルを持ったクリニックが地域で積極的な連携を図ることが、地域医療の進展に繋がると思います。