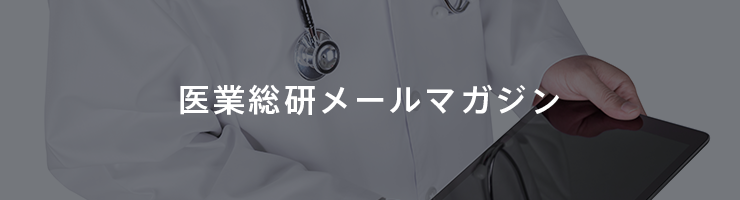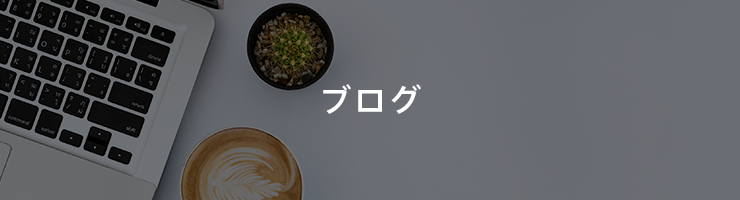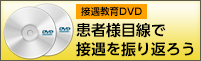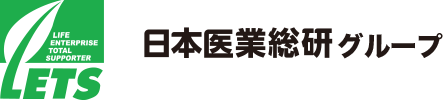女性の一生のステージに寄り添う医療
世界屈指のお産安全国といわれながらも、一方で産婦人科医数自体は増加に転じたものの、まだ足りていないという声が止まないようです。先生が産婦人科に入局されたころの医療現場環境はいかがでしたか。
医師の絶対数というより、問題は地域偏在でしょうね。東京は施設数自体が多いので、ある程度充足していますが、地方の産科医不足は解消されていません。ただ、産科婦人科に入局した当時の私は、医師の数など関係なしに毎月20日間くらいは夜勤をしていました。
月に20日といったら勤務日のほとんどということですね。
そうですね。そういう時代でもあったし、私にとっての貴重な修行期間でもありました。
進路としては、産科婦人科一択だったのですか。
研修中は循環器内科に進もうかと迷っていました。父が内科医でしたので、その影響もあったかと思います。最終的に産科婦人科を選んだのは、医局研修での婦人科の内視鏡下手術を見学し、鮮やかでスピーディな手技に魅了されたことです。若手医師にどんどん手術経験を積ませて育てていくという医局の方針にもポジティブな共感を覚えました。
開業前に産婦人科クリニックの赤枝医院(多摩市)に勤務されていたようですが、これは自院開業を意識してのものでしょうか。

自院開業は早くから意識のなかにありましたが、赤枝医院での約3年間の勤務で、開業・運営にかかわる一通りのノウハウを学ばせていただきました。本当にいい勉強になったと思っています
先生にとっての産婦人科医療の面白さ、やりがいはどういったところでしょうか。
妊娠・出産全般にかかわる産科と、女性特有の疾患や幅広いトラブルを診察・治療する婦人科は、それぞれ個別の領域だととらえています。ただ、女性が初潮を迎え、閉経するまで、年齢を重ねるに従い不調や疾患の種類が変わっていきます。そうした一生のステージに寄り添い、お役に立てることが産婦人科の特徴です。私自身は病院勤務医時代から腹腔鏡を用いた骨盤臓器脱手術など骨盤外科に取り組む一方で分娩にも魅力があって、無痛分娩の立ち上げなども経験してきましたから、医師としてのやりがいに溢れた診療科だと思っています。
日帰りを可能にした子宮鏡手術

自院開業で実現したかった医療、病院ではなくクリニックならではのサービス提供をどうお考えですか。
不妊症や不正出血で悩まれる方のなかには、子宮に病気が隠されているケースが少なくありませんが、子宮内膜ポリープや子宮粘膜下筋腫などは、内視鏡下での手術で十分に改善が期待できます。病院だと入院が必要となることが多いのですが、当院では日帰りが可能ですので、そこを強く押し出していこうと考えています。
病院の場合、医療機能上、入院治療が前提になる部分があるのでしょうが、日帰り手術が可能となると、患者さんの受診のハードルも下がりますし、大きな強みになりそうですね。
日帰り手術の実施には、医師の技術的なものと、医療環境の問題があります。内視鏡手術となると、基本的に術者の多くが大きな病院に勤務しています。病院は多職種の連携で日々運営しているので、あらかじめ検査・手術・入院・退院の日時が設定・管理され、あまり融通が利きません。日帰りが可能と思われる場合でも、その患者さんだけ個別に対応するというのは現実的に不可能なのです。私自身、なんとか上手く時間を短縮できないものかと考えていましたが、だったら自院開業で実現しようという感じです。
女性特有のデリケートな悩みも含め、みなさん少なからず不安を抱えて受診されると思われますし、治療自体も決して快適なものではないでしょう。そうした女性患者さんのメンタリティにどう向き合い、どのように不安を和らげるように対応されていますか。
丁寧な会話で、突き詰めていくしかありません。受けたい医療を選ぶのは患者さんです。不安を持たれることも当然で、どうして手術が必要なのかをじっくりと話して、納得をしていただかなければなりません。自らの意思で治療しなければという意識をもっていただけるまでコミュニケーションを図ります。治療以前に、信頼関係を築くことに一番時間を使うといってもいいでしょう。

患者さんの不安を和らげる人的サービスという意味では、先生と同じ考えに立ったスタッフの接遇なども大切になりますね。開業ではどういう基準で採用を決められたのですか。
立ち上がりは看護師2名、受付2名体制で予算計画を組みましたが、それぞれ1人は前職からの知り合いに入職していただきました。人選に悩む先生も多いという話をうかがいますが、元同僚で私の性格や診療スタイルなども理解している方々ですので、クリニック運営のパートナーとして大いに期待しています。
スタッフとの日常的なコミュニケーションで、実践されていることはありますか。
形式ばった定例ミーティングのような形ではありませんが、適宜、スタッフの意見を聞きながら対応の方針を確認し、書面で渡すなどのことはしています。ただ、婦人科の経験者もいるので、私が指示するまでもなく自らの状況判断で動いてくれています。そこは心強いところです。
子宮頸がんをはじめ、婦人科で診る悪性腫瘍の種類は多くあります。がんに対する、予防や早期発見・早期医療介入に対して、どういった啓蒙や促しをやっていこうとお考えですか。
とくに啓蒙といえるものは、いまはしていません。みなさん、受診のきっかけが欲しいのでしょうけど、自覚症状がないと面倒だし、診察自体が嫌だという意識もあるのでしょうね。ただ、おりものの悩みや、生理痛で来られた患者さんも含め、当院に来られた方には、最低でも年1回は来ていただけると、病気が見つかることもありますということはお伝えしています。
患者さんとは、構築された信頼関係をベースに長いお付き合いになるかと思います。そうなると、年齢とともに、自費分野であるアンチエイジングなどのニーズも多くなると思われます。先生は、どう対応しようとお考えですか。
一応、アンチエイジングの専門資格も持っていますが、いまのところ積極的な働きかけはしていません。需要の広がりはあるのでしょうが、エビデンスが確立されている療法が少ないのが現実です。その説明に患者さんが納得され、求められれば、ビタミンの点滴などは行っています。それで少し気分がリフレッシュされたり、肌のツヤが戻った気がすることで満足いただければいいのではないかと思っていますし、それでも、リピーターが結構いらっしゃいます。出会いのきっかけはどうであれ、そこから、婦人科にかかわるお悩み全般にわたるお付き合いができるといいですね。実際に、勤務医時代に出産を担当し、20年経って健診で当院に来てくださる方もいらっしゃいます。
院長自ら足を運び、紹介を促す積極的な働きかけ

事業計画では、保険と自費の割合をどの程度に想定されていたのですか。
(小畑「日本医業総研」)立地的に自費の需要がある程度見込めるのではないかと考えましたが、事業計画自体は、ほぼ保険診療で組み立てました。ただ、立ち上げてみると保険の手術件数が思った以上に多く、恐らく高江洲先生もここまで入るとは、予想されていなかったのではないでしょうか。
(高江洲先生)子宮鏡の手術自体、マイノリティな領域で、全国的にもそんなには普及していませんし、実施している病院も限られているということがあるのではないかと思います。ただ、不妊治療にも付随してくる医療ですので、需要は必然的に増えていくのではないかと思っています。
(小畑)それをクリニックでやられるというのは、私自身初めて経験しましたし、だからこそ、紹介が多く出るわけですね。
(高江洲先生)病院だと、どうしても入院が負担に感じられるのでしょうね。当院のホームページから日帰りで受けられることを知って来られる方も少なくありませんが、やはり紹介が一番多いですね。
紹介というのは、どういったルートからなのですか。
知り合いの病院に開業の挨拶で回ったほか、まったく関係のなかった医療機関にも自分でアポを入れて直接出向いての説明に努めました。やはり顔が見えないと、関係性も築けませんから。
紹介に応じる意味でも、お茶の水という立地選定は正解だったかもしれませんね。
都心で、JR線が使え、駅近の物件という条件で、小畑さんにお願いした結果です。自宅との兼ね合いから、中央線沿線を中心に複数の候補地をピックアップし、それぞれに診療圏調査での見込み患者数を出し検討をしました。その結果、お茶の水がベストという結論に至りました。結果として、小畑さんの判断は的確だったと思っています。

当社、日本医業総研は、2019年に五反田で開業されたKARADA内科クリニックの佐藤昭裕先生からの紹介でしたね。
そうです。佐藤先生は大学の水泳部の後輩で、医局は違うのですが、卒後も親しく付き合ってきました。すでに本院を拡張し、渋谷に分院も出され盛況されているようですね。その佐藤先生が、「絶対間違いないから」ということで、日本医業総研の小畑さんにサポートを依頼することになったわけです。
立ち上がりから現在までの好調な経営数値について、高江洲先生としてはどのような評価をされていますか。
最初の5月~6月はどうなることかと不安が先にあって、小畑さんにも随分相談してきましたが、手術の紹介が増えたことで、ようやく軌道に乗ってきた感じで、単月で黒字化できそうです。手術を当院の強みに、このまま伸ばしていこうと思いますが、次にどんな医療を提供していこうかと考えている途中です。
今回の弊社の開業サポートについての忌憚のない評価をお聞かせください。
小畑さんには本当に多くの時間を投入していただきました。物件も結構沢山見させていただき、比較検討できたことで、納得度の高い開業ができましたし、思い通りの医療提供実現に近づいてきていると感じています。更に成長し、拡張や分院展開というステージを迎えられたら、また小畑さんにお願いしたいと思っています。
院長プロフィール
院長 高江洲陽太郎 先生
医学博士
日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医・指導医
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医(腹腔鏡・子宮鏡)
日本内視鏡外科学会専門医
日本産科婦人科遺伝診療学会 周産期認定(周産期)
日本抗加齢医学学会専門医
母体保護指定医
2005年 東京医科大学 卒業
東京医科大学病院 臨床研修医
2007年 東京医科大学 産科婦人科入局
東京医科大学 茨城医療センター
2008年 東京医科大学病院 助教
国立病院機構 横浜医療センター
2009年 東京都保健医療公社 大久保病院
日立総合病院
2015年 社会福祉法人 聖ヨハネ会桜町病院 産婦人科部長
2020年 糸数病院
赤枝病院
2024年 お茶の水たかえすレディースクリニック 開設